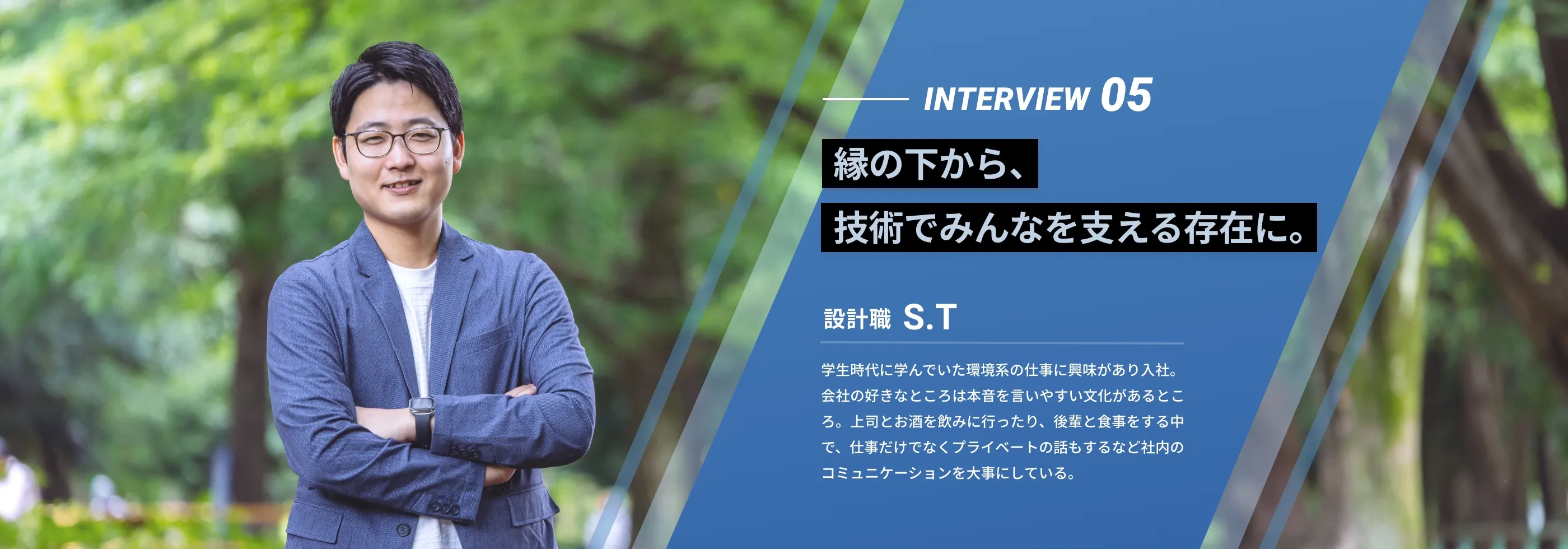
-

「水」は環境にとって超重要。水処理に思いっきり関われる会社へ
幼少期から森や木などの自然を大切にする意識があり、大学時代は環境系の専門分野で勉強をしていました。大学で水環境の保全の授業があり、地球で使える水は本当に少ないと教えてもらったとき、なんとなく「おもしろいな」と思ったのがきっかけで、就職活動では水にまつわる仕事を探していました。そして、水処理メーカーや水処理装置を扱っている会社を見ている中で、西原ネオと出会ったんです。中小企業は、人が少ないので、自分ができる仕事の幅が広いんじゃないかなと思っていたのですが、誰でもできるような仕事も嫌で、何か手に職をつけられる仕事がいいと思っていました。西原ネオはジョブローテーションの文化もあって、いろいろな経験も積めますし、水処理のプロとして極められることがいいなと思い、入社を決めました。
-

踏み出すことこそ推奨される。西原ネオ流の教育
特に若手のうちこそ、仕事を受け身ではなく、まずは動いてみる意識が大事だと思います。最初に配属された電気設計の部署で、先輩と1つの案件に携わりながら勉強をしていたんですが、急遽行うことになった打合せの前に先輩がお休みを取っており、何も分からないまま立ち止まってしまったんですよね。そしたら、当時の上司が「たたき台だけでも作ってみたら?」と声をかけてくれ、自ら一歩を踏み出す勇気をくれました。動いてみて学べることも多くて、分からないことが多い若手の時こそ、まずはやってみる、という意識が大事なんだと痛感したんです。そして、もう1つ大切なのが見聞きすることを鵜呑みにせず、自ら納得をつくること。設計だと「どうしてその設計にしたのか」という質問は絶対に聞かれます。なんとなくではなく、設計するもの1つひとつにいつでも説明できるような納得感を持つことが大事になります。その先に自分が自信を持って考え抜いたものを世に出せるという達成感に繋がるんですよね。なので、新人時代は自ら考え行動することで自身の力がついていきますし、仕事が面白くなるはずです。
-

ブレイクスルーのきっかけになったジョブローテーション制度
入社から3年間ずっと設計グループにいたのですが、4年目の時に「現場に行くか?」と聞かれて施工管理の仕事を経験しました。もともとこのまま設計職として図面を描いていても、成長しないのではないか?という思いがあって、一度現場を見てみたかったんですよね。そんな時に声がかかったので、チャンスが舞い込んできたと思いました。その時の現場は今でももう一度やり直したいと思うくらい改善点がありましたが、本当にたくさんのことを学ぶことができました。設計の一番の難しさは、図面を描いている時にイメージをすること。配管一本にしても、どうやって施工するのかを実際に目で見たことで、イメージできるようになったのは大きいと思います。普段自分が描いていた図面の現場の様子がイメージできるようになって、その後の設計の仕事も変わりました。水槽のレイアウトひとつが変わると、配管ができなくなったり、機器の配置も変えないといけなかったりするのが自然と思い浮かぶようになったんです。設計をする中で、上司から新しいアイデアやシンプルな設計にするためのアドバイスをもらいますが、以前より自分の意見を持って協議できるようになったと感じています。
-

設計をはじめとしたスキルを、仲間やお客様のために磨き続ける
設計は他の職種とは違いお客様と顔を合わせることは少ないのですが、営業から聞いたお客様の要望に合わせて、オーダーメイドのものを生み出していることは縁の下の力持ちであるという「貢献している」という実感がありますね。私は、頼られる人間になりたいという想いがあって、それは単に認められたいとかの話ではなく、頼っている、頼られるという状況には必ず誰か困っている人がいるということ。それを少しでも自分の手で解消したいと強く思いますし、それが私のやりがいに繋がっています。だからこそ今は、自分のやるべき範囲を決めないことを大事にしています。自分ではできない、設計の仕事ではないと決めない。例えば営業へ図面を渡した後に間違いに気づいて修正をしたとしても、もしすでにお客様に提出していたとなると、そのミスでお客様からの信頼が揺らぐことがあるんですよね。自分はお客様とやりとりはしませんが、仲間である営業の立場も考えて、仕事をすることが大切だと思っています。設計図を工事に引き渡す時、後は施工管理の仕事のような気がするんですが、工事中に起こる設計の修正を手伝ったり、施工方法の提案をしたりするだけでも、ありがとうという感謝と信頼し、信頼される関係が生まれるんですよね。私はそんな仲間を思った設計者として、頼られる自分であり続けたいと思っています。

